2026年1月30日更新。サイトの表示速度を向上させました。記事の内容を一部追加しました。
こんにちは、学びライフです!
今回は、「生徒会経験をどう推薦入試で活かすか」についてお話しします。
私自身、生徒会活動を通して得た経験を面接や書類でどう表現すればいいのか、とても悩みました。
特に「頑張ったこと」をただ書くだけでは伝わらない、それが推薦入試の難しさでもあります。
この記事では、
・生徒会経験が評価される理由
・面接・志望理由書での効果的な書き方
・実際に使えるフレーズ例
を中心に紹介します。
その他にもこのブログでは推薦入試に関する記事を投稿していますので、参考にしてみてください。
【保存版】推薦入試で生徒会経験をどうアピールする?|志望理由書・面接で使える例文つき – 学びライフ
【元生徒会長の大学生活】推薦入試で国立大学に入学した僕が伝える入学後のメリットとデメリット – 学びライフ
なぜ生徒会経験は推薦入試で評価されるのか?

生徒会活動は、学校生活の中でも特に「主体性」が求められる場です。
そのため、大学の先生や入試担当者は次のような点を重視しています。
① 主体的に行動した経験があるか
生徒会では、自分から考え、周りを動かしていく力が求められます。
ただ「任された仕事をした」ではなく、
自分で考えて改善した・新しい取り組みを提案した という姿勢が評価されます。
特に行事への姿勢や生徒会で取り組んだ企画について具体的なエピソードを用意しておくのが良いかと思います。
② 協調性・リーダーシップがあるか
生徒会はチームで動く場です。
「周囲の意見をまとめた」「後輩を支えた」「先生と話し合って企画を進めた」など、
人と関わる中で発揮した力が大切です。
リーダーシップに焦点が当たりがちですが、チームで活動する場合は他の人と一緒に協力して取り組めることも大切です。
なので、チームでの話し合いが円滑に進むようにサポートをした、というようなエピソードでも重要な武器になります。
③ 困難をどう乗り越えたか
どんな活動にもトラブルや壁はあります。
それをどう解決したか、どう気持ちを切り替えたか。
その経験は、「問題解決力」「忍耐力」として評価されます。
大学での学習や社会で重視されるのは、その人がしっかりと自分で考えて主体的に問題を発見して、それに取り組むことが出来るかどうかです。
どんな取り組みにも主体的に取り組む必要があるため、生徒会経験者はぜひ志望理由書や推薦書の自己PRで取り入れることをおすすめします。
私自身も、大学受験の推薦入試での志望理由書や面接の回答として、しっかりとこの部分をアピールしたことで無事に合格することが出来ました。
志望理由書に書くときのコツ

生徒会経験を志望理由書に書く場合、
「活動 → 学び → 将来の志望」 の3段構成で書くのがポイントです。
例文構成
① 活動内容(何をしたか)
私は中学・高校で生徒会に所属し、行事の運営や学校生活の改善に取り組みました。
② 学び(そこで得たこと)
その中で、意見の違う仲間と話し合いながら一つの目標を達成する大切さを学びました。
また、人前で話す機会を通して自分の考えを言葉にする力が身につきました。
③ 将来へのつながり(なぜこの学校なのか)
この経験を生かして、貴学ではチームで課題解決に取り組み、
より多くの人の役に立つ研究・活動を行いたいと考えています。
このように、「何をしたか」よりも「そこから何を学んだか」を明確に書くと伝わりやすくなります。
詳しくは以下の記事で扱っているので、参考にしてみてください
【テンプレ付き】元生徒会長が志望理由書・自己推薦書の書き方のおすすめの構成と書く時のポイントを4つ紹介! – 学びライフ
🗣 面接で話すときのポイント3つ

① “エピソードを短く具体的に”
基本的には推薦入試で聞かれることは、志望動機や将来の展望、学生時代に取り組んだことが聞かれますが、生徒会執行部に所属していたような人たちは、
「生徒会活動で一番印象に残っている出来事を教えてください」
と聞かれることが多いです。
他の面接の質問を答える時も、同様ですが
事実→行動→結果 の順で簡潔に話しましょう。
💬 例:
体育祭のスローガンを生徒全員で決める企画を提案し、
アンケートをもとに言葉を集めました。
最終的に学校全体で意見がまとまり、皆が誇りを持てる行事になりました。
話す時間は1分以内が目安です。
私が高専の推薦入試を受験した時には、このように簡潔に自分が取り組んだ事柄を説明することが出来なかったため、面接官からの印象があまり良くなかったです。(だから落ちました。)
そのため、大学受験の推薦入試では面接の質問への解答を、簡潔に答えられるように先生方や友達と繰り返し練習をしました。
文章を前もって考えるのも良いかもしれませんが、入試の当日は考えた内容を忘れてしまうので
絶対に言わないといけないキーワードを準備しておくようにすると良いかと思います。
② 失敗談を「成長」に変える
面接では「うまくいかなかった経験を教えてください」という質問もあります。
その場合、反省ではなく「次にどう行動したか」を語ることが大切です。
💬 例:
行事の準備で連絡がうまく取れず、当日混乱してしまいました。
その後、担当ごとに共有ノートを作り、
情報を一か所にまとめる工夫をしました。
このように、改善策を話すと前向きな印象になります。
③ 笑顔と姿勢を意識する
緊張していても、姿勢と目線だけで印象は大きく変わります。
生徒会での司会や発表の経験を思い出しながら、
「聞いてもらう姿勢」ではなく「伝える姿勢」で話すことを意識しましょう。
よくあるNGパターン
| NG例 | 改善ポイント |
|---|---|
| 「生徒会で頑張りました。」 | → 何をどう頑張ったのかを具体的に。 |
| 「協力の大切さを学びました。」 | → どんな場面で、どう感じたかを添える。 |
| 「将来に活かしたいです。」 | → どんな形で活かすのかを明示する。 |
例:「将来に活かしたい」ではなく
「将来は、人の意見をまとめる力を生かしてチームを支える立場になりたい」
のように、“行動の方向性”まで伝えると強いです。
面接の対策についても以下の記事で紹介しています。
【推薦入試対策】元生徒会長が面接が苦手な人・緊張しやすい人へ回答の考え方と面接のポイントを7つ紹介! – 学びライフ
推薦入試が不安な方へ:生徒会での活動を合格に直結させるために
「うちの子、生徒会ばかり頑張っていて受験は大丈夫かしら……?」
「推薦入試の対策を学校の先生としているけど、本当にこれだけで合格できるのかな、、、?」
そんな不安を抱えている保護者の方、そして、生徒会経験者の子は少なくありません。勿論、自分自身もそうでした。
しかし、元生徒会長の私からお伝えしたいのは、「生徒会の経験は、最高の合格武器になる」ということです。
ただし、それには条件があります。それは、活動の記録を「ただの思い出」ではなく、
「大学が求める実績」へ正しく翻訳することです。
実は、生徒会経験者の多くが「見せ方」を知らないだけで、推薦入試において圧倒的に有利な立場にいます。
もし、お子様のこれまでの努力を確実に「合格」という形に変えたいのであれば、学校の先生だけに頼らず、一度プロの視点を取り入れてみることを強くおすすめします。
推薦入試が幅広く広まってきた現在において、
自力や学校の先生だけでは他のライバルに差を付けられる可能性がかなり高いです。
私が推薦入試対策の観点から信頼しているのが、「総合型選抜専門塾AOI」または、「早稲田塾」です。そして、日々の生徒会活動や部活動と両立して、苦手を克服しやすい「ウィズスタディ」です。
【保護者向け】お子様に最適な「推薦対策塾」の選び方
生徒会経験を「合格の武器」に変えるためには、お子様の性格に合った環境選びが不可欠です
| 比較項目 | 総合型選抜専門塾 AOI | 早稲田塾 | ウィズスタディ |
| 最大の特徴 | 合格率94.1% の実績 | 伝統の 「論文作法」 | 「安さ」と「学習管理」 |
| 主な費用 | 個別指導につき要相談 | 講座・学年により変動 | 1科目9,800円〜 (税込) |
| こんな人に | 推薦入試の結果を最優先したい | 一生モノの文章・思考力を得たい | 生徒会と勉強を両立させたい |
| 強み | 生徒会実績の「武器化」 | 2万人超の膨大な合格データ | 現役医学生など実績のある講師による1対1徹底コーチング |
| 最初の一歩 | AOIの無料カウンセリングへ申し込む | 難関私大の総合型選抜で圧倒的合格実績! | 無料体験授業を受ける |
推薦入試で実際に国立大学の理系学部に合格した私からのアドバイスとして、理系的・元生徒会長な視点で見ると、
AOIは「個別の最大化」、早稲田塾は「基礎力の底上げ」に強みがあります。また、推薦入試だけではなく、「学習計画をプロに伴走してもらう選択肢」としてウィズスタディもおすすめです。
どの塾も、まずは両方の無料カウンセリングや資料請求を行い、お子様との相性を確認することが、
合格への最も論理的な第一歩です。
一度親子で確かめてみてはいかがでしょうか。
なぜこの3つ?国立大理系生による「忖度なし」の選定基準
ネット上には多くの塾紹介があふれていますが、私は「自分が現役時代にこれがあれば125万円の損失を防げたか」という基準でしか紹介しません。工学部でシステム設計を学ぶ視点から、以下の3つの「論理的必須条件」をクリアしたサービスのみを厳選しています。
① 「活動実績」を「研究者レベルの論理」へ翻訳できるか
2026年度入試(探究学習評価型)では、単なる思い出話は1円の価値もありません。生徒会での試行錯誤を「課題設定→仮説→検証」という理系的なPDCAサイクルへ翻訳する力があるか。AOIや早稲田塾はこの「言語化」において圧倒的な合格データを持っています。
② 生徒会特有の「カオスなスケジュール」に耐えうるか
行事直前は塾どころではなくなるのが役員の宿命です。固定の授業カリキュラムではなく、個別の状況に合わせて学習を最適化(最適化問題の解決)できる柔軟性があるか。特にウィズスタディのオンライン管理は、多忙な役員にとって最も効率的な「外注先」になります。
③ 125万円の損失(私立入学金25万)を回避する「国立大合格率」
国立大理系は4年間の学費が安く、家計への貢献度は最大です。一般入試で「滑り止めの私立」に25万円を捨てるリスクを最小化し、第一志望の国立大への勝率を1%でも引き上げる実績があるかを重視しています。
本サイトでは、読者の皆様に公平な判断基準を提供するため、消費者庁のステルスマーケティング規制を遵守しています。紹介しているサービスは、国立大学工学部(ロボット工学専攻)に在籍する運営者が、自身の合格体験と周囲100名以上の受験データに基づき、論理的合理性が高いと判断したプロモーションのみを含んでいます。
AOIの無料カウンセリングに申し込む↓
早稲田塾の資料請求をする↓
難関私大の総合型選抜で圧倒的合格実績!ウィズスタディの無料体験に申し込む↓


ちなみに以下の記事では,塾選びの方法についてまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください
【失敗しない】生徒会経験を活かす「推薦入試対策塾」選び。国立大理系学生が教える3つの評価基準 – 学びライフ
私自身の体験から伝えたいこと

私が初めて生徒会に立候補した理由は、
中学1年の頃に2か月ほど不登校を経験し、
「誰もが学校に行きたいと思えるような場所にしたい」と思ったことでした。
最初の演説では緊張で声が裏返り、思い通りに話せませんでしたが、
原稿を工夫して伝えたい想いをしっかり言葉にできたことで、無事に当選できました。
その後も行事の企画や司会を通して、
自分の中に「責任感」と「アドリブ力」が育っていくのを感じました。
しかし、その際に培ったアドリブ力を過信して高専の推薦入試に臨んでしまったことで、高校受験は失敗しました。
ただ、そのときの悔しさを生かして、しっかりと推薦入試に向けた準備を行ったことで、
失敗した経験が、大学の面接でも自信を持って話せる“自分だけの物語”になりました。
あくまでも、生徒会での経験は誰でも推薦入試で合格出来るようになるような
肩書きではないので、
自分の強みを表現するエピソードの1つとして、手を抜かずにしっかりと準備するようにしましょう。
気になる人は以下の記事を参照してみてください。
高専に落ちた時に行っていたことなどをまとめてみました。
【俺みたいになるな!】高専の推薦入試で落ちた時に僕がやっていたこと3選 – 学びライフ
まとめ|あなたの生徒会経験は“最高の自己PR”

- 生徒会での経験は「行動力」「協調性」「問題解決力」の証
- 志望理由書では「活動→学び→将来」を意識して書く
- 面接では短く具体的なエピソードで伝える
- 失敗も前向きに話せば、強みになる
あなたの経験は、決して「平凡な学校生活の一部」ではありません。
誰かのために動き、自分と向き合い、挑戦した日々そのものが、
何よりも説得力のある「あなたの物語」です。




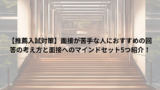
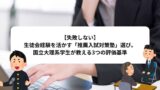



コメント