2026年1月29日更新。サイトの表示速度を向上させました。記事の内容を一部追加しました。
こんにちは、学びライフです!
今回は、生徒会活動の中でも意外と悩むテーマ…
「文化祭・体育祭などの予算の組み方」について解説します。
「お金のことって難しそう…」
「予算ってどうやって決まるの?」
と感じている生徒会役員の方も多いのではないでしょうか。
実は、行事の成功は「予算の使い方」で大きく変わります。
限られたお金でも工夫次第で、より充実したイベントをつくることができるんです。
この記事では、
・ 予算の基本構造
・ 予算の立て方と配分のコツ
・ 節約・工夫のアイデア
・ 実際に私が経験した予算トラブルと解決法
を、分かりやすくまとめました。
ちなみに生徒会活動は実は推薦入試で最高の「武器」になります。
私自身、生徒会経験を生かして推薦入試で国立大学への合格を果たしました。なので、少しでも推薦入試を考えている人は以下の記事を読んでみてください。
【保存版】推薦入試で生徒会経験をどうアピールする?|志望理由書・面接で使える例文つき – 学びライフ
そもそも予算ってどう決まるの?

文化祭や体育祭の予算は、学校によって決め方が異なります。
あくまでも私の経験とはなりますが、大抵の場合は
次のような流れでお金が割り振られます。
- 学校(またはPTA・生徒会予算)からの行事費が決定
- 生徒会で全体の配分を検討
- 行事の実行委員会・各クラス・各部門に割り当て
- 会計担当が行事の前後で支出内容を確認・承認
- 行事後に決算報告を提出
つまり、生徒会は「お金を管理する役」ではなく、
“どう使えば全体がより良くなるか”を考える調整役です。
生徒会の活動では先生との連携が必要不可欠です。以下の記事では先生との良い関係を作るアドバイスをまとめているので、ぜひ読んでみてください
【保存版】先生との関係づくり・上手な連携方法|生徒会活動をスムーズに進めるためのコツ – 学びライフ
🗓 予算づくりの流れ(1ヶ月半前から)

大きな行事の予算は、行事の1ヶ月半前から準備を始めるのが理想です。
主に生徒会の中でも会計担当の人が大きく動くことになるとは思いますが、生徒会全体として情報の共有をしっかりと行っておくようにしましょう。
【ステップ①】前年データを確認
- 前年度の文化祭・体育祭の支出記録をチェック
- どんな費目にどれくらい使われたかを把握する
もしデータが残っていない場合は、前任の役員や先生に聞いてみてください。また、お金が関わることなので、データが残っていたにせよ、会計担当の先生と情報を共有するようにしておくと良いかと思います。
【ステップ②】使い道を洗い出す
費目を明確にすると、予算の見積もりが立てやすくなります。
先生と一緒に作成するか、先生方が過去のデータから大まかな使い道を教えてくれるかと思います。
ただ、生徒会が新しい取り組みを行う場合は先生に提案書を提出した上で見積もりについても書面でまとめておく必要があります。
【文化祭の例】
- 装飾・看板材料費
- 音響・照明機材レンタル費
- 印刷・ポスター・パンフレット費
- 販売用食材費(飲食ありの場合)
【体育祭の例】
- 放送設備・マイク・スピーカー
- 表彰用の賞状・トロフィー
- 会場整備費・ラインテープ・カラーコーン
- 応援グッズ・ゼッケン・Tシャツ代
私の場合はコロナがあったため、前年度と全く異なる取り組みをすることになり、取り組みの提案書だけではなく、何を買わないといけないのか?などもまとめる必要があったため、かなりバタバタしました。なので、生徒会執行部全体で分担して取り組んでおくようにしましょう。
【ステップ③】配分を決める
全体予算が決まったら、
「必要性」と「全体の公平性」を意識して配分します。
例:
- 全体装飾や会場設営は全校共通の支出
- クラス・団体ごとの活動費は人数に応じて均等割り
- 生徒会・委員会は運営に関わる最低限の経費に絞る
私はいつも、「学校全体に関わる支出」→「団体(学年やクラス)単位の支出」→「個別企画の支出」の順に予算を分けていました。
学校によっても、取り組み方に特色があると思うので前年のデータをしっかりと確認しておくようにしましょう。
予算表の作り方(テンプレ)
| 費目 | 内容 | 見積金額 | 実際の支出 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 装飾費 | 看板・風船・紙花など | ¥8,000 | ¥7,650 | 問屋でまとめ買い |
| 音響費 | マイク・延長コードなど | ¥3,000 | ¥2,800 | 既存備品を再利用 |
| 印刷費 | パンフレット・ポスター | ¥5,000 | ¥4,500 | 校内印刷で節約 |
| その他 | 応援グッズ・予備費 | ¥2,000 | ¥1,900 | 未使用分を返金 |
→ ExcelやGoogleスプレッドシートで共有すると、複数人で管理しやすいです。
私の場合は生徒会室内のパソコンのExcelでまとめていました。
節約・工夫のアイデア

① 余り物・再利用をうまく使う
過去のイベントの装飾・備品は意外と再利用できます。
看板板材・布・テープなどは捨てずに保管しておくのがおすすめ。
② 企業・地域に協力をお願いする
文化祭では、地元の企業から備品や広告協賛をもらうケースもあります。
(例:お菓子メーカーから提供、印刷会社にポスター協力など)
ただし、必ず先生の許可を得てから進めましょう。
③ 校内制作でコストカット
印刷・音響・装飾など、外部業者に頼まなくてもできることは校内で完結させます。
私の学校では、美術部に看板デザインをお願いして経費を削減していました。
各部活も協力してもらうことで学校全体としてのまとまりが出来るので、積極的に協力してもらうといいかもしれません。
よくある失敗と対策
| よくある失敗 | 対策 |
|---|---|
| 費目を忘れて後から予算オーバー | 全支出をリスト化して見える化 |
| 各団体が自由に使いすぎてバラバラに | 最初にルールを共有する |
| レシート・領収書の紛失 | 支出担当を1人決めて管理 |
| 未使用分を返さない | 必ず決算報告で精算する |
1番多いのは、レシートや領収書の紛失です。
各クラスの会計担当の人に何度も念を押して、レシートや領収書の管理が出来ているかの確認を行うように伝えると良いですね。
行事が終わった後には反省が必要不可欠!以下の記事ではそんな行事の反省について、知っておいて欲しいことをまとめていますので、ぜひ読んでみてください。
【保存版】生徒会向け|行事後の振り返りと反省会の進め方|次回に活かす5つのコツ – 学びライフ
私の体験談

生徒会長をしていた時、前年と異なる企画をすることになったため、
文化祭の予算で想定より2倍に膨らむかもしれないというトラブルがありました。
そこで、
- 材料をまとめて購入して全クラスで分ける方式にする
- 各クラスで出来るだけお金を抑えられるような工夫を凝らした所に賞を与える
- 購入ルールを文書化し、申請制に変更
この改善で予算内で行事を完了できました。
まとめ|「お金の使い方」も立派な生徒会の仕事
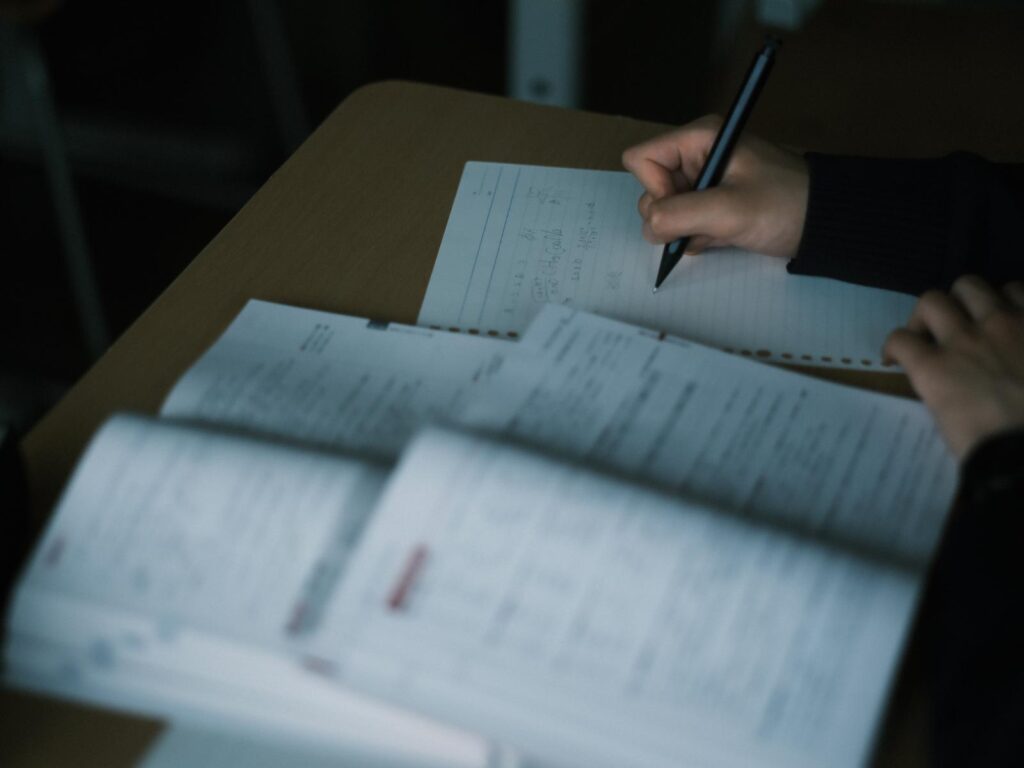
文化祭や体育祭の予算づくりは、「数字を扱うだけの仕事」ではありません。
限られたお金で最大限の価値を生み出す工夫を考える力が問われます。
- 前年度データをもとに準備を始める
- 公平な配分と透明な管理
- 無駄を省いて、創造的に使う
この3つを意識すれば、行事のクオリティもぐっと上がります。
お金をうまく使える生徒会は、どんな学校でも信頼されますよ。




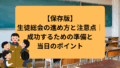

コメント