最終更新 2026年1月29日 記事の読みやすさを改善しました。記事の内容を一部追加しました。
こんにちは、学びライフ運営者です!
今回は、生徒会活動の中でも特に大きな行事である「生徒総会」についてまとめました。
「生徒総会って何をすればいいの?」「どう進めたらいいの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
私自身も、生徒会長として初めて総会を担当したときは、準備量の多さと緊張感に圧倒されました。
ですが、流れや注意点を押さえておけば、安心して当日を迎えることができます。
この記事では、
・生徒総会の目的
・準備の進め方
・当日の流れと司会のコツ
・よくあるトラブルと対処法
を、実体験を交えて解説します。
ちなみに生徒会活動は実は推薦入試で最高の「武器」になります。
私自身、生徒会経験を生かして推薦入試で国立大学への合格を果たしました。なので、少しでも推薦入試を考えている人は以下の記事を読んでみてください。
【保存版】推薦入試で生徒会経験をどうアピールする?|志望理由書・面接で使える例文つき – 学びライフ
生徒総会とは?目的を明確にしよう

生徒総会は、学校全体の生徒が意見を出し合い、学校生活をより良くするための話し合いの場です。
具体的には以下のような目的があります:
- 生徒会活動や委員会の報告を行う
- 校則や学校ルールへの提案・意見を共有する
- 生徒全体の意見を集約して、先生方へ届ける
つまり、「生徒会が代表して決める場」ではなく、
“全校生徒が学校づくりに参加するための会”なんです。
将来の政治にも繋がる、大切な行事なので力を入れて取り組むことをおすすめします!
なので、その生徒全体の意見をしっかりと把握して、以降の生徒会執行部としての活動の方針を定める大切な行事になっています。
私自身、この行事をきっかけにして校則を変えたり、これまでの行事の内容に生徒の要望を踏まえて改善をしたことがあります。
🗓 準備の進め方(1ヶ月半前からが理想)
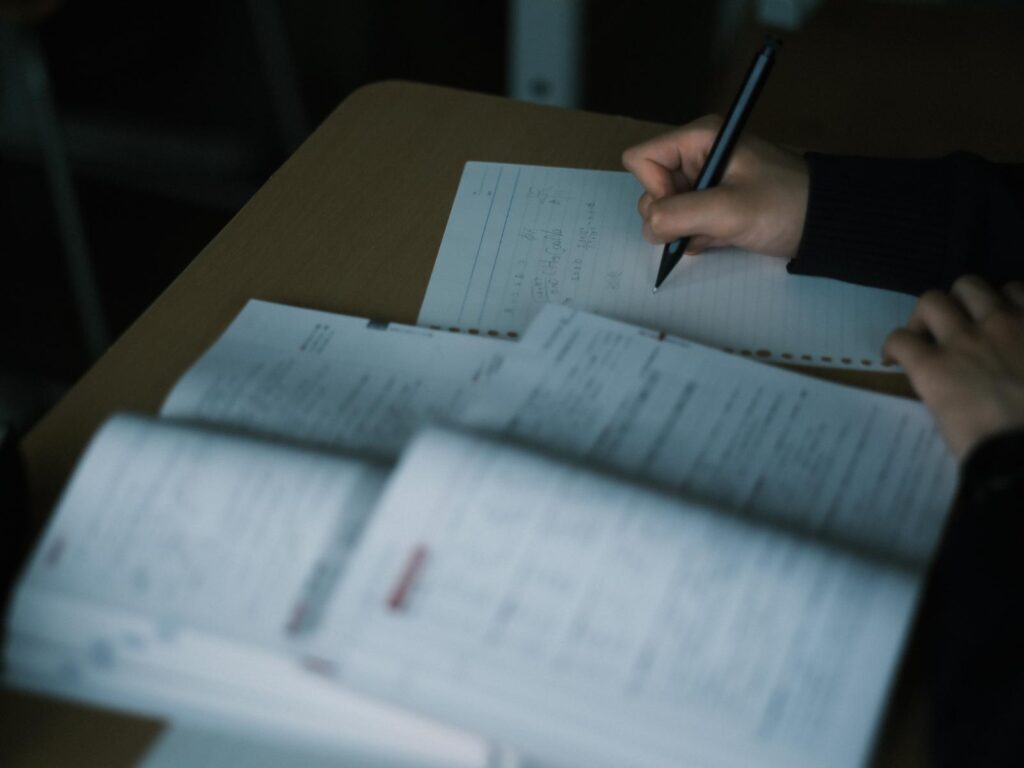
生徒総会の準備は、行事の1ヶ月半前から始めるのがおすすめです。
ギリギリだと、資料づくりや意見回収が間に合いません。
また、大抵の場合は、生徒総会で校則を変える提案や行事で行いたい新しい取り組みについてを、全校生徒へ提案することになります。
そのため、もしも学校全体を大きく変えるような取り組みを考えている場合は、
少なくとも、生徒総会の3カ月くらい前から生徒会執行部の担当の先生へ企画書を提出して、職員会議で生徒会からの提案の裏取りをしておくべきだと思います。
また、当日までに各役員のバインダーを用意しておくことをおすすめします。
行事当日は、進行表や役割分担表、台本などを何度も確認する場面があります。
私たちの生徒会では、それらを バインダーにまとめて持ち歩く ようにしていました。
必要な資料をすぐ取り出せるので、当日の進行がスムーズになり、先生との確認も簡単になります。
生徒総会に向けて、沢山やりたいことがあるけど担当の先生とあまり仲良くない、、、、
という方は以下の記事を読んでみると良いかもしれません。
私自身、先生との関係性はとても気をつけながら生徒会活動に取り組んだことで、少し厳しい生徒会担当の先生に校則の改正のサポートを行ってもらうことが出来ました!
【保存版】先生との関係づくり・上手な連携方法|生徒会活動をスムーズに進めるためのコツ – 学びライフ
【ステップ①】議題を決める
生徒会役員・各委員会から議題を集めて整理します。
各委員会における議題と、生徒会執行部全体としての議題があります。
基本的には各委員会の議題はそれぞれの委員会で受け持ち、三役は生徒会執行部全体の議題に取り組む、という役割分担をすると良いかもしれません。
例:
- 校則の見直しについて
- 行事の改善点
- 新しい取り組みの提案 など
※議題は多すぎると時間内に終わらないため、3〜4件が目安です。ただ、学校によるかとは思いますので担当の先生や引き継ぎの資料をしっかりと確認するようにしてください。
【ステップ②】意見を集める
議題が決まったら、クラス単位で意見用紙やフォームを配布します。
このとき、意見用紙は引き継ぎの資料のものを再利用してもかまわないですし、新しく作成してもいいかと思います。自分の場合は引き継ぎの資料のものをパソコンで編集して、新しい項目を付け足したり、校則の変更に伴う意見を募るフォームを追加しました。
意見書を変更する場合は先生に確認することを忘れないようにしましょう。
ポイント:
- 全員が発言できるよう、匿名形式でもOK
- 1クラスにつきまとめ役(議長補助)を決めておくとスムーズ
私はGoogleフォームを使って集めたこともあり、自動で集計ができて、とても便利でした。
各学校によって様式が用意されている可能性もあるため、しっかりと確認するようにしてください。
意見を集めたい場合は以下の記事が参考になるかと思います。
【保存版】生徒会活動で使えるアンケートの作り方と使い方|行事・校則・意見収集に大活躍すること間違い無し! – 学びライフ
【ステップ③】原稿・資料づくり
生徒会で討議内容をまとめ、「総会資料(議案書)」を作成します。
基本的には書記の方の役割になるかと思いますが、資料はこまめに三役で確認して、先生とも情報共有を行いながら作ることをおすすめします!
- 表紙(日時・目的)
- 各議題の内容
- 生徒会・委員会の報告
- 意見の要約と回答案
などです。これについても当日に行う内容に合わせて追加して、柔軟に作成する様にしてください。
印刷や配布は1週間前までに完了しておくと安心です。
【ステップ④】リハーサル
リハーサルは、前日または当日朝に必ず行いましょう。
私は高校の頃にリハーサルをせずに取り組んだことで、当日に予期せぬ音響のトラブルが起きて進行に支障が出てしまったことがあります。
特に重要なのは:
- 司会・議長のセリフ確認
- 発表者の立ち位置・順番
- マイクの音量・資料投影テスト
ここを省くと、当日の進行が大きく崩れます。
必ず、先生に確認した上で行うようにしましょう!
🎤 当日の進行の流れ

実際の生徒総会は、学校によって多少異なりますが、基本の流れは以下の通りです。
私の生徒総会の経験を元に流れを解説しようと思います。
【1】開会宣言・挨拶
司会「これより、生徒総会を始めます」
→ 生徒会長または顧問の先生の挨拶
※ここで全体の雰囲気が決まるので、明るく・ハキハキと話すのがポイントです。
【2】活動報告
- 生徒会・各委員会が1年間の活動を報告
- 代表者が要点を簡潔に説明(1団体あたり1〜2分)
- その後、生徒全体に向けて、疑問点がないかの質疑応答
話すのが苦手な委員会の方は必ず、台本を用意して活動報告に臨むようにした方がいいかと思います。
【3】議題審議
ここがメインパート。議題ごとに以下の流れで進めます。
校則の変更といった重要度の高い内容は最後の方に持ってきて、重要度の低い内容から議題を進めるとスムーズに進行できるため、おすすめです。
- 司会が議題を読み上げる
- 生徒会から提案・説明
- 生徒から意見・質問を受ける
- 生徒会が回答・補足
- 採決 or 次回へ持ち越し
発言が出にくいときは、「○○クラスの意見では〜とありましたが、皆さんはどう思いますか?」と促すと効果的です。
【4】まとめ・閉会
- 議長「これで全ての議題が終了しました」
- 生徒会長の挨拶
- 閉会宣言
最後に「生徒の声を学校に届ける機会をつくってくれてありがとう」という感謝の言葉を入れると雰囲気が和らぎます。
よくあるトラブルとその対処法

| トラブル | 対処法 |
|---|---|
| 発言が少ない | 事前にクラスで意見を出してもらう or 司会が例を出して誘導する |
| 時間オーバー | 議題を3件以内に絞る or 発言時間を短くする |
| 質問が偏る | 委員会メンバーにも質問を分担して答えてもらう |
| マイク・機材トラブル | 予備マイク・印刷資料を用意しておく |
| 会場がざわつく | 開会時に「静かに聞いてくれてありがとう」など感謝の言葉を添える |
他の行事でもそうですが、想定できそうなトラブルやリハーサルを行うことで防げそうなものは、出来るだけ本番で起こらないように対策をすることが大切です!
私の体験談

私が生徒会長を務めたときの生徒総会では、
最初の議題で意見が全く出ず、会場が静まり返ったことがありました。
その時、司会をしていた議長の方が機転を利かせて、
「では○○クラスの意見を紹介します」と話を振ったことで流れが戻りました。
その経験から学んだのは、
“会議は準備と柔軟さで決まる”ということです。
まとめ|生徒総会は「みんなで作る行事」

生徒総会は、生徒会だけのイベントではありません。
全校生徒・先生・委員会が一体となって学校を良くする機会です。
- 早めの準備(1ヶ月半前から)
- 明確な議題と資料づくり
- 柔軟な進行とフォロー体制
この3つを意識すれば、きっとあなたの学校でも意見が活発に出る“生徒らしい総会”を作れます。
この総会をきっかけに政治にも興味が湧くかと思うので、ぜひ力を入れて取り組んで貰いたいと思います!
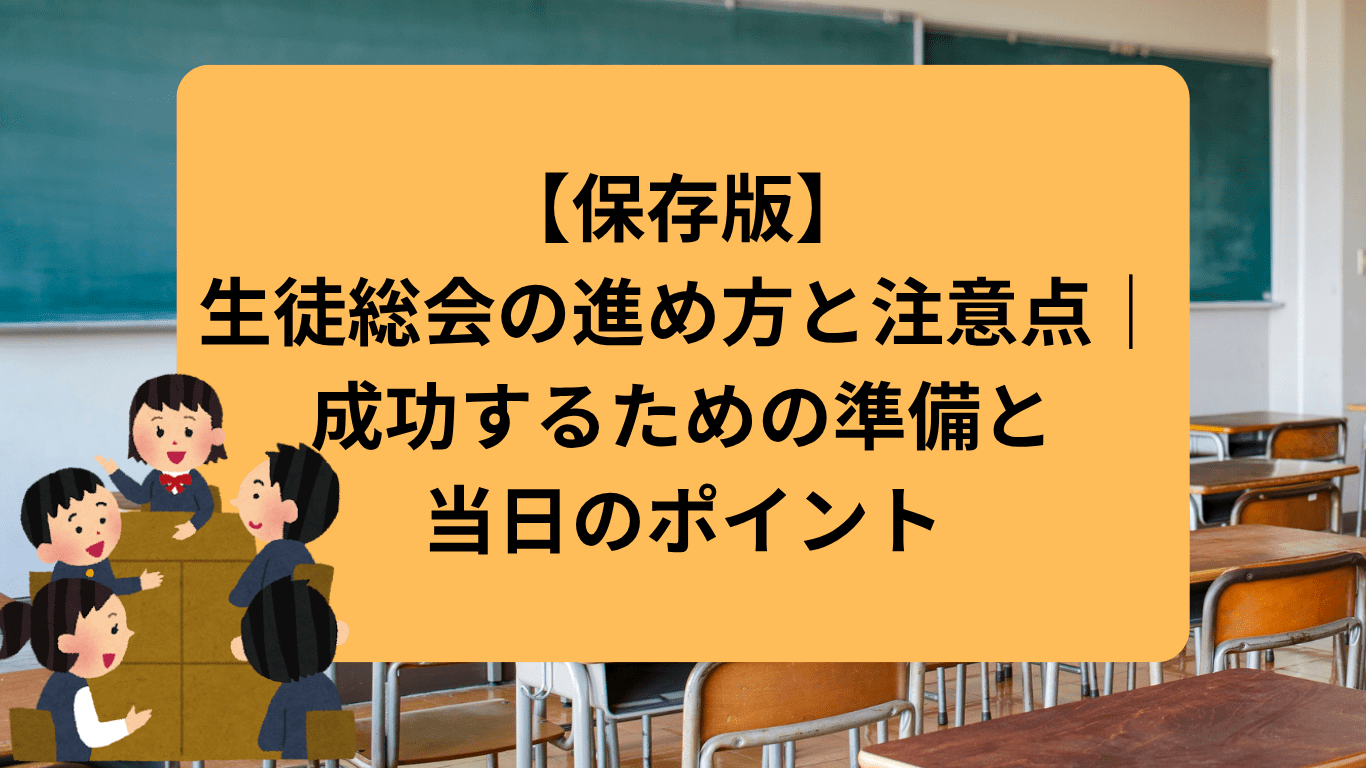





コメント